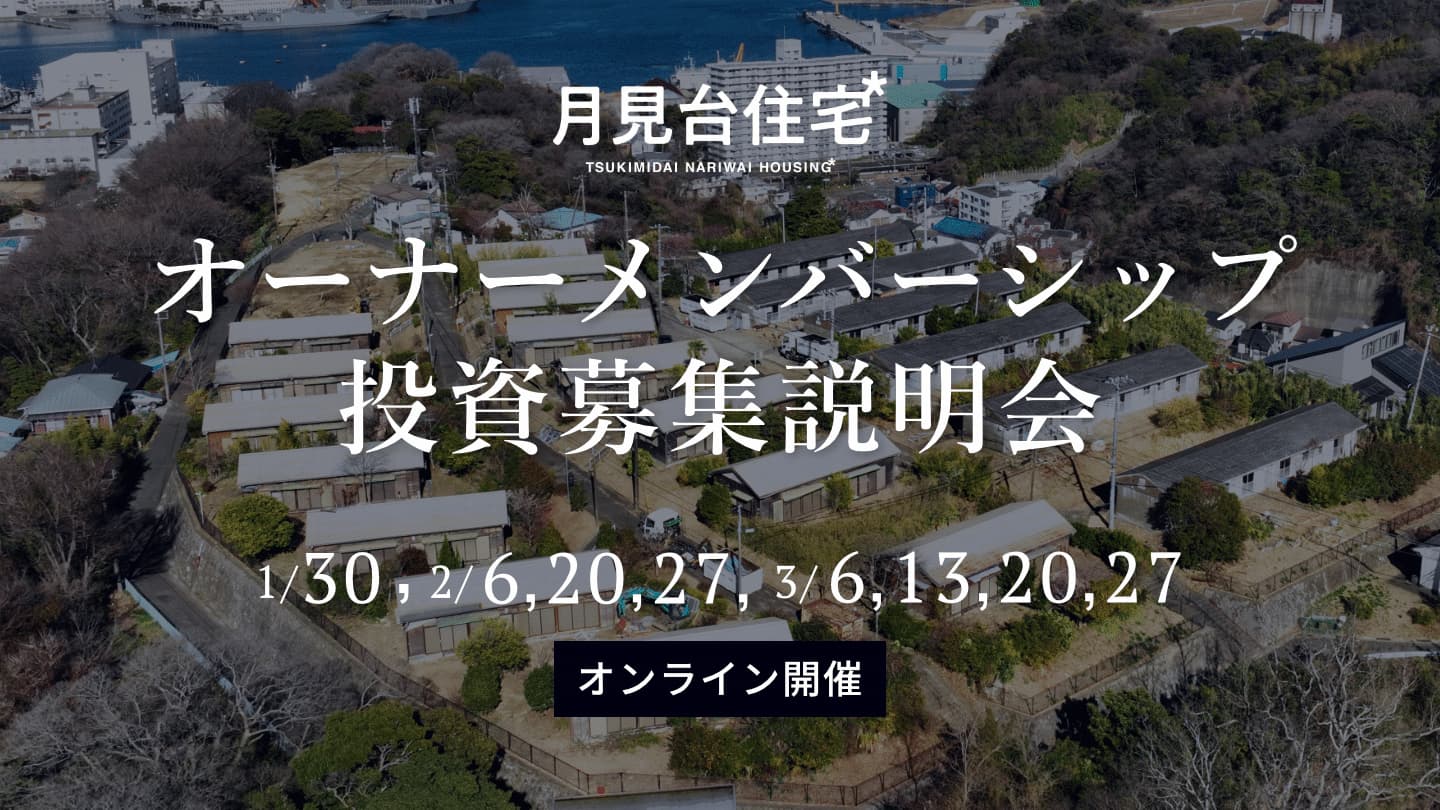小規模不動産特定共同事業とは? 創設の背景や概要、事業例、再生事例を解説

少子高齢化が進むなか、全国で空き家が増加しています。地方創生を実現するためには、空き家など遊休不動産の再生利活用が重要です。国土交通省は近年、新しい不動産業の可能性を切り開くため「小規模不動産特定共同事業」を創設しましたが、登録事業者数は今年9月現在で48社*1とさらなる普及促進が求められます。事業概要や創設の背景、事業例、地域住民や投資家が主体的に関わる仕組みを取り入れた地域共創プロジェクトの事例について分かりやすくお伝えします。(最新更新日:2023年4月1日)
1. 不動産特定共同事業法とは
業務の適正な運営の確保と投資家の利益の保護を図ることを目的に平成6年に制定された制度で、出資を募って不動産を売買または賃貸し、テナントに貸し出すなどして得た収益を投資家に配分する事業のことをいいます。
平成25年に不動産特定共同事業法の一部が改正され、倒産隔離型スキーム(特例事業)が導入されました。また、平成29年の法改正では小規模不動産特定共同事業(小規模不特事業)が創設されるとともに、クラウドファンディングに対応した環境が整備されました。これによりインターネット上での契約締結を可能とする電子取引業務に係る規定が整備され、事業者はインターネット上で一般の投資家からお金を集めてさまざまな事業を行うことができるようになりました。今後の成長拡大が見込まれる事業モデルです。
不動産特定共同事業者(許可制)主な許可要件
- 資本金(第1号事業者:1億円、第2号事業者:1000万円、第3号事業者:5000万円、第4号事業者:1000万円)
- 宅建業の免許
- 良好な財産的基礎、構成かつ適確に事業を遂行できる人的構成
- 基準を満たす契約約款(一般投資家を対象とする場合のみ)
- 事務所ごとの業務管理者配置(業務経験や一定の資格が必要)
2.小規模不動産特定共同事業創設の背景
従来の不動産特定共同事業を手掛けるには、国や都道府県の許可が必要であるほか、資本金や監査などの条件もあり、参入のハードルが高いことが課題となっていました。さらには、地方創生に資する事業においてもクラウドファンディングを用いた資金調達が広がるなかで不動産特定共同事業も電子化への対応が必要であること、そして質の高い不動産ストックの形成を促進するためにも不動産特定共同事業制度の規制の見直しが求められていました。こうした背景から平成29年に法が改正され、投資家からお金を集めて空き家や古民家を再生する事業の規制を緩めて小規模な事業者の参入を容易にする環境を整えました。
小規模不動産特定共同事業者(登録制)に関する主な制限、要件の違い
- 投資家一人あたりの出資額及び投資家からの出資総額がそれぞれ原則100万円、1億円を超えないこと
- 資本金(小規模第1号事業者:1000万円、小規模第2号事業者:1000万円)
3.地方創生における不動産特定共同事業活用の意義と事業例
「地元の遊休不動産(公的不動産も含む)を、人の流入・雇用創出・地価上昇につながる施設に再生・整備したい」というニーズに対し、伝統的な資金の出し方では開発や融資側のリスクが大きく、また外部から開発事業者が現れても地元主導ではない画一的な不動産開発となる恐れがあります。
そこで、不動産特定共同事業を活用した「地域ファイナンス」や、共感投資による個人からの資金調達、投資家による施設利用・事業への継続関与により、単なる資金調達にとどまらず事業の好循環まで確保できる事業を生み出せる可能性があります。
(小規模)不特事業に該当する事業には、例えば下記のようなものがあります。
例1:遊休店舗・戸建等を取得し、再生後、事業者等に賃貸する
投資家からの出資をもとに空き店舗の所有者から不動産を取得し、リノベーション工事を実施後、宿泊事業者や店舗経営者などのテナントに賃貸し、賃貸事業から得られる賃料収益をもとに投資家へ分配を行う事業。一定期間運用後は、第三者等に売却して事業を終了し、売却益をもとに投資家へ配当を行います。

国土交通省「小規模不動産特定共同事業」パンフレットより
例2:土地を取得し、店舗・住宅等を新築した後、売却する
投資家からの出資をもとに、空き地となっている土地を取得します。その後、戸建住宅等の新築を行い、竣工後は第三者等へ売却します。その売却益をもとに投資家へ配当します。

国土交通省「小規模不動産特定共同事業」パンフレットより
4. 不動産クラウドファンディングを用いた参加型の不動産再生事例
それでは実際に小規模不特事業の活用事例を見ていきましょう。身近な遊休不動産を住民の流入や雇用創出、地域の価値向上をもたらす施設に再生する。これこそが、地方創生における不動産特定共同事業活用の意義です。
ここで紹介する事例はいずれも投資家に金銭リターンのほか、投資額に応じて施設利用の特典を付与するなど遊休不動産の再生事業自体に共感する投資家から投資がなされる仕組みがあります。
2018年6月、エンジョイワークスが日本初の小規模不動産特定共同事業者となり、第1号募集ファンドで開業した一棟貸しの宿泊施設「泊まれる蔵プロジェクト」(神奈川県三浦郡葉山町)を紹介します。事業の特徴や物件概要、リノベーション資金、ファンド募集金額などについても触れていますので、小規模不特事業に興味のある方はぜひ参考にしてください。エンジョイワークスは、以降もさまざまなプロジェクトのファンド募集を行っています。
(1)第1号ファンド<葉山>泊まれる蔵ファンド

2018年6月、600万円募集
三浦郡葉山町にある約12坪の小さな蔵を1日1組限定の「泊まれる蔵」にリノベーション。さまざまな宿づくりへの参加の仕掛けを用意し、クラウドファンディングを実施、募集スタートし、わずか1日で目標募集額の600 万円を達成しました。銀行融資と合わせた合計の事業資金は1,600 万円です。1階はラグジュアリーなバスルームとソファを据えてくつろげる空間に、2階は最大4名が泊まれる小上がりのあるベッドルームに改修。コロナ禍でも順調に運営を継続しています。
物件の概要
所 在 地:神奈川県三浦郡葉山町堀内901番地
用途地域:近隣商業地域
敷地面積:約100㎡(駐車スペース2台と庭部分を含む)
床 面 積:1階19.83㎡、2階19.83㎡
構 造:木造2階建
築 年:不詳(オーナーによると100年超)
契約形態:7年定期借家
主なリノベーション工事内容
1 階:断熱工事・壁塗装、床レベル調整、天井塗装、階段の製作・掛け替え、ジャグジー、洗面、トイレなどの水回り設備等の整備
2 階:断熱工事・壁塗装、床補強・塗装、ベッド・収納等の造作作成
その他:外構、ガス引き込み

(2)第2号ファンド <逗子>桜山シェアアトリエファンド

2018年8月、1,200万円募集
逗子市桜山の廃工場を地元のアーティストたちが集うシェアアトリエにリノベーション。希望の物件がなくて困っている人達と個人投資家で開いた、「そんな物件ねーよ!」をつくる会議が発端でした。リノベーションにはアーティスト達もDIY で参加し、オープン前から予約で埋まり、その後も満室稼働を続けていた物件です。前オーナーが売却するに当たり、ファンドが物件を購入しました。
(3)第3号ファンド <銀座>カプセル保存再生ファンド

2018年11月、350万円募集
黒川紀章氏設計の世界的名建築「中銀カプセルタワービル」の一つのカプセルを、「マンスリーカプセル」として多くの方にカプセル暮らしを経験していただくためにリノベーション。世界的にもファンが多いにも関わらず、将来の解体もありうる状況の名建築の保存再生へ繋げることを目指しています。
このほか、国土交通省の資料で、第4号および第5号ファンドを募集した事業も紹介されています。あわせてご覧ください。
第4号ファンド <鎌倉>旧村上邸再生利活用ファンド 2019年3月より 900万円
第5号ファンド <京都>五條楽園エリア再生ファンド 2019年3月より 4,000万円
国土交通省「不動産特定共同事業(FTK)の利活用促進ハンドブック」
5. 小規模不動産特定共同事業における課題と、事業成功のポイント
(1)小規模不動産特定共同事業における課題
小規模不特事業の取り組みに係る「登録要件」「案件組成」「運用段階」という各フェーズにおけるボトルネックのいくつかは、国の取り組みや企業のサービスによっておおよそ解消することができます。また、小規模不動産特定共同事業における一般的なフェーズは次の通りです。

小規模不特事業の流れ(イメージ)
出典:空き家の利活用ためのファイナンスに関する調査研究報告書
そこで課題として残るのは「事業性の確保」ができるかどうかという点です。事業の収益性を確保するためには、低廉な価格の物件を見つけて付加価値をつけ、調達コストの低い資金を集める必要があり、事業者の力量が問われます。具体的には物件ソーシングの能力、目利き、付加価値をつける能力、他者を巻き込む力などが挙げられます。そのため小規模不特事業の実施にあたっては案件組成段階から他事業者との連携を視野に入れることも重要です。
(2)不動産特定共同事業の成功のポイント
投資家の共感を得るための工夫として「不動産特定共同事業の利活用促進ハンドブック」には次のようなポイントが挙げられています。
- 金銭以外のリターンの提供
- プロジェクトの意義やコンセプトなどの積極的な発信
- 地域のシンボル整備やエリア全体の価値向上を打ち出す
地域に求められる施設を地域資金によって整備することにより、投資を追求するだけでなく地域の資金循環を構築し、持続可能なまちづくりの実現が可能になります。さらに、官が大規模な修繕を実施した建物について民間に事業運営を任せたり、補助金の交付や地代の減額を実施したりすることにより、民間事業者単独では事業化できない場合でも官民が連携して事業に取り組むことが重要であることも述べられています。
私たちエンジョイワークスは「小規模不動産特定共同事業者」の登録を日本で初めて行い、共感投資プラットフォーム「ハロー! RENOVATION」で、複数のプロジェクトの資金調達を達成しています。
行政と民間事業者だけでなく、市民も含めた共創ができる仕組みとして、場づくり段階からの積極的なSNS発信、イベント開催、投資型クラウドファンディングを活用した市民も出資し事業参加できる仕組みを提案。事業計画も投資家や地域住民が主体的に関わることができるよう組み立てており、参加型まちづくりの成功事例として評価いただいています。
2022年度には国土交通省 令和4年度 住宅市場を活用した空き家対策モデル事業採択事業として「不動産ファンド活用方法セミナー」を全国6カ所で開催。全国の不動産事業者を対象に、増え続ける空き家・遊休不動産の再生や利活用のために不動産ファンドを活用する際の法規制上の考え方や事業の組み立て方、資金調達スキームについてお伝えしました。
これらの知見を活かし、小規模不動産特定共同事業者の登録をサポートしています。地域一丸となって取り組む空き家再生によるまちづくりに関心のある方はお問い合わせください。
問い合わせはこちらから
エンジョイワークスについて
エンジョイワークスは、不動産、建築、まちづくり、空き家再生・利活用などの取り組みを行っている企業です。「みんなで一緒にまちづくり」をテーマに住まいや場所、コミュニティに関するプロデュースを行っています。創業以来、地域のさまざまな遊休不動産を活用したカフェ、シェアオフィス、宿泊施設などを運営する中で得た課題解決のナレッジを全国の空き家問題にも展開すべく、事業とコミュニティの価値を学び参加することができる、共感投資プラットフォーム「ハロー! RENOVATION」の運営を開始。さらには実践的な解決ができる高度専門人材を育成する「次世代まちづくりスクール」の運営も行っています。
関連資料
*1 小規模不動産特定共同事業者登録一覧(令和4年9月30日時点)
*2 国土交通省「不動産証券化の実態調査」
*3 国土交通省「不動産特定共同事業の利活用促進ハンドブック」
参考資料
空き家の利活用ためのファイナンスに関する調査研究報告書(全国宅地建物取引業協会連合会 / 全国宅地建物取引業保証協会)
不動産特定共同事業(FTK)の利活用促進ハンドブック(国土交通省)
*本記事は、2022年11月19日公開の記事を再編集したものです。


![オルタナティブな投資とは?カピバラ好き行政書士・石井くるみさんと学ぶ不動産クラウドファンディングの最先端[開催レポート]](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/hello-renovation/img/uploads/2019/08/15145815/01-660x371-1.jpg)