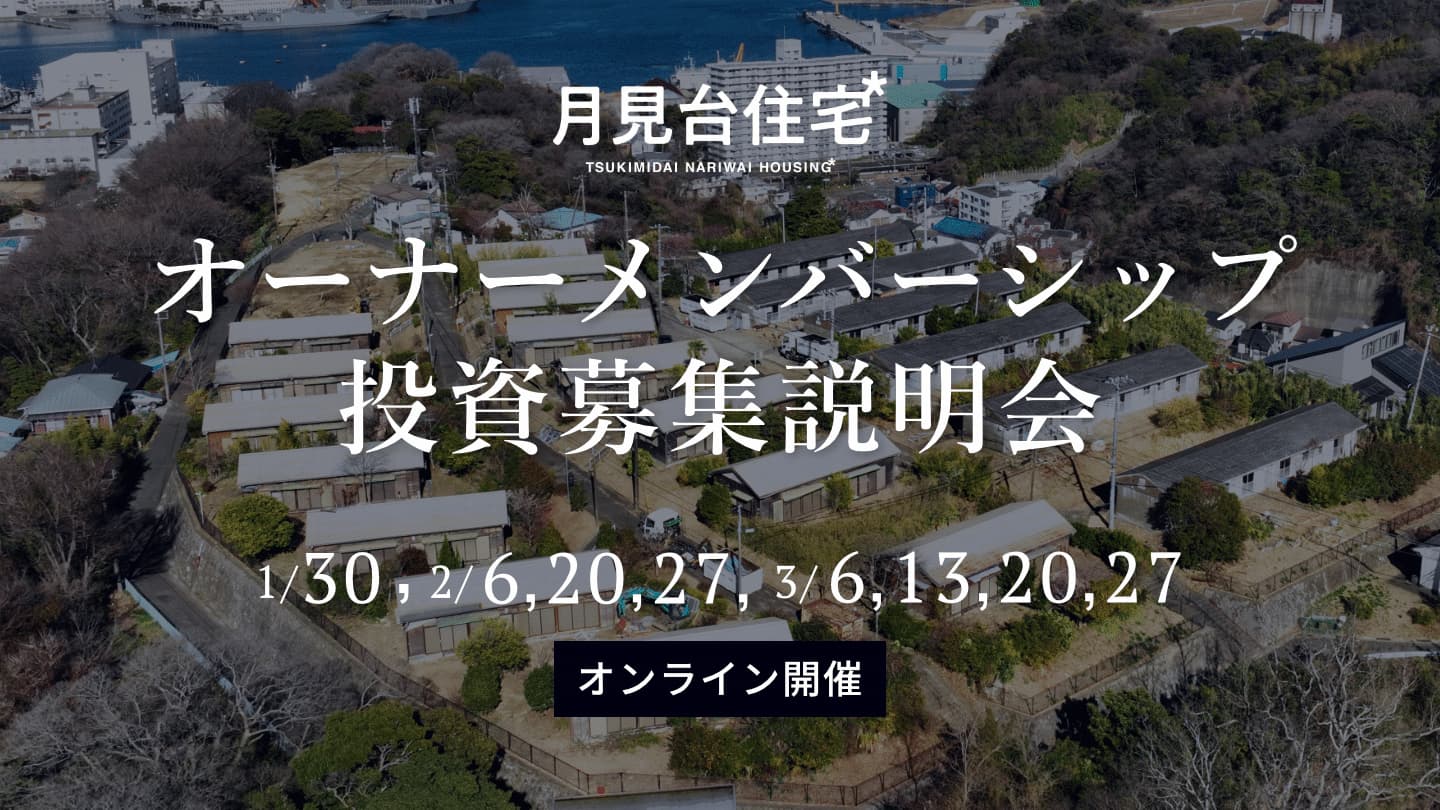地域密着での重度障害者の住まいづくり。母親として、オープンに周囲を頼り共に考える

重度障害者の地域密着の住まいづくり「たまよんガーデン・コミュニティープロジェクト」(通称、たまよんプロジェクト)が、速水葉子さんの主導で始まります。少し前に、速水さんに自己紹介をお願いした時に、お話をされたのは、雅子さんとのお話でした。
親子の30年を振り返っていただき、伝えていただくことで、障壁や課題を私たちも知っていくことになります。無知では力になれませんし、並走できません。まずは背景や事実を知る。これから先のつながりのためにできることを、共に考えます。これから関わっていただく多くのみなさんに、知っておいていただきたいという想いから、速水さんの言葉でこれまでを伝えさせていただきます。
雅子について 障害がわかるまで
雅子は1987年5月11日、予定日より1週間遅れて生まれました。胎動が少なめだとは感じていましたが、妊娠中特に異常もなく、とてもスムーズな短時間のお産でした。ただ、低体温だったのと、月数にしては体が小さめでやや黄疸が出ていたので、5日間保育器で過ごし、7日で通常の退院をしました。
よく静かに眠る赤ちゃんでした。異常に気づいたのは、2ヶ月過ぎた頃から。長男の時は2ヶ月ともなれば、首も座り始め、目を合わせて声をあげて笑い、喃語(なんご)も始まっていのに、雅子は目が合わず、首も座らず、お乳の飲み込みも悪い。何かが違うと感じ始めていました。結局4ヶ月目の保健所での定期診断を迎える前には、眼科、小児科を廻り歩き異常を見つけるのに必死になっていました。最終的に脳波異常が見つかり、普通には育たない、おそらくはかなり重い障害を持つと告げられた時には生後5月に入っていました。当然、目の前は、真っ暗になり、夫婦で寝られない夜を何日も過ごしました。

ですが、私がこの頃自分に強く誓ったことは、自分の心だけは閉じないようにしよう。隠さず、人にも話し、情報をとり、助けてもらえそうな人、機関には援助の手を差し伸べてもらおうと。長男の通っていた保育園の園長先生にまず相談し、「発達」という雑誌をお借りして帰ったのを覚えています。
体が弱く、すぐ風邪をひいたり、発熱することも多く、その間に、定期的に障害者専門の病院に1時間以上かけて通い、整形外科、脳神経内科の診断、リハビリ訓練を受けるのです。食事を始める頃になると、食事指導が入り、帰ってから、習ってきたリハビリを行うので、どんどん普通の育児、家族の時間がなくなり、特別な赤ちゃん、特別な家族になっていく感覚がありました。今でも忘れない風景は、まだ新しい建物だった専門病院で診断を待つ時の風景。外には綺麗な芝生が整えられ、遊具が置かれている。だけど、順番を待つ親子でその遊具を使って外で遊ぶ人はいません。役立たずの遊具がなぜかとても寂しく気持ちをさらに暗くしました。
それまでは、より良い病院、プレステージの高い医師、より効果のある療法、訓練法を求めて、追いかけていた私でしたが、このままでは、普通の子育て、家族の時間がなくなってしまう。近くの公園で遊ぶ気力も残っていない生活はまずい、と強く感じ、当時続けていた特殊な訓練の指導以外は、遠い病院へ行くのをやめようと決め、専門病院の系列のより近くにある病院での定期診断に切り替えました。
雅子の状態は何回か検査入院をしましたが、本当の原因がわからぬまま、結局「広義」の脳性麻痺との診断となり、1歳からは発作が出たので点頭てんかんがそこに加わりました。最初は目も見えていないだろうと言われるほど、表情が乏しく、首も座らず、笑顔もたまにしかでなかったものの、1歳をすぎたころから物に手を伸ばす反応が現れ、笑顔が自然に出てきました。相変わらず首は座らず、お座りもハイハイもできない状態でしたが、子供の声によく反応することがわかり、いろいろな刺激を受け、同年代の子供たちと交流させたいと強く思うようになりました。
同年代の子供と出会える場所はどこか、近隣の幼稚園をいくつか当たりましたが障害が重いことから断られ、1園キリスト教関係の幼稚園がぜひどうぞと言ってくれたのですが、地元から離れ、車で送り迎えする毎日は、娘の体力では無理だろうと諦めました。
同時期、訓練で訪れていた、京都の病院のカウンセラーさんから「重度の障害であればあるほど、お母さんの世界がその子の世界になるから、絶対に世界を狭くしてはいけない。」と言われたことに背中をおされ、自分も仕事をやれる範囲で続けて行こうと決心していました。当時はワープロもまだ出始めで、訳稿は手書きでしたが、鉛筆と辞書、原稿があればどこでも翻訳の仕事は続けられるという思いでした。

保育園、遊びでつながる時代
長男の通っていた近くの公立保育園には2歳の時から申し込みを続けましたが、障害の重さを理由に断られ続けました。であれば、遊びにいかせてくださいとお願いして、週に2−3日、お昼までの遊びの時間に親子で混ぜてもらうようになりました。同じ場で育つことの意味の大きさを学んだのはこの頃でした。子供たちは率直に、なぜ娘は動けないのか、喋れないのかなど、疑問を投げてくれるのでわたしも子供にもわかるように丁寧に答えるようにしていました。一緒に遊んだり散歩したりするうちにだんだん仲間として受け入れてくれる感覚を覚えました。
公立保育園への入所の希望を夫も一緒に役所に出向いて、気長に訴えを続けました。そのうち、保育園でお昼もお弁当を持って昼食の場面にも混ぜていただけるようになり、そして最後の1年はついに「正社員」として公立の保育園に入ることができたのです。保育園のママ友ができたのもこの頃です。保育園に正式に入ってからは、親御さんたちにも娘の障害のことは努めて説明するようにしておりました。道で会っても保育園のママやお子さんに「雅子ちゃん、」「まこちゃん」と声をかけてもらえるようになっただけで、こんなに自分の気持ちが元気になれるのかと心が軽くなるのを覚えました。


養護学校や学童、ボップ、地域交流の難しさ
こうした経験を経たので、養護学校(現特別支援学校)に入学することになっても、区と交渉の末、1年生のときから学校の帰り地域の学童に通いました。寝たきりで、ごろごろしかできない娘でしたが、彼女のゆったり、ゆっくりさが好きなお子さんは、同じ部屋でごろごろくつろぐようになり、おやつの時間、娘にすすんでおやつをあげる係になってくれる子も現れました。

3年間のなかで一番感動したのは、お誕生日に初めて近所のお友達に呼んでもらえたことでしょうか。娘の誕生日にも学童のお仲間にもきてもらいました。夏の学童のキャンプも家族で参加し、川遊びもゴムボートにのせて楽しむことができました。こうして、3年間はあっというまに過ぎました。せめて「遊び」で繋がれる間は地域の子供と交流してほしかったのです。同じ学童の仲間に協力してもらって、学童への通所の延長を区に打診しましたが、認められませんでした。

そこで当時、区で学校の運動場を所属児童に対して遊び場として解放するボップ(BOP: Base Of Playing:遊びの基地)という制度が始まったばかりでしたので、所属の小学校の生徒ではないが、地域の子として遊びにいくことを認めてもらえないかと学童のお母さんたちも協力してくれ、区に掛けあいました。長男の通った小学校で、PTAの知り合いのお母さんがボランティアとしてボップに参加していたこともあり、現場の職員さんとともに、受け入れにむけて協力体制を作り、待っていてくれましたが、最終的には「特例をつくれない」ということで、ボップへの参加も叶いませんでした。
ちょうどその頃、雅子は病気で父を失うことになりました。10歳の誕生日を目前にした日でした。地域のつながりをなるべく自然なかたちで保ちつつ子育てしたいと思っていた私でしたが、そこでプツンと糸が切れてしまった状態になりました。以後、養護学校を卒業するまで、地域とのつながりを特段育む努力もせずに過ぎていきました。
再び考える「楽しい」ことで繋がる地域での仲間づくり・ドラムサークル
病弱で学校を休むことも多く何度も肺炎で入院する状態であった雅子も思春期にはいり太れるようになると体調も安定する日が多くなり、当時養護学校に併設されていた、週に何日か泊まれる寮での先生たちとの出会いもあり、養護学校生活は充実した楽しいものとなりました。
わたしは相変わらず仕事とケアの間をいったりきたりの毎日ではありましたが、障害のあるお子さんたちの音楽のクラスやイベントで、太鼓や、音の出るおもちゃで、参加する子供たちのうれしそうな姿を何度も目にする機会がありました。メロディー楽器はハードルが高くてもリズムを刻むだけで参加できるリズム音楽の楽しさを実感し、障害が重くてもこれは楽しめるし、一緒に演奏できる、できれば、もっと音のいい楽器、リズム専門で指導してくれる人がいたら楽しみ方も発展できるのではと考えていました。
また一方で福祉の助けに感謝しながらの毎日ではありましたが、障害児、障害者となるとどうしても福祉の文脈の中にいれられてしまうことに息苦しさも覚えていました。養護学校を卒業したら、次は通所施設に通う毎日が待っています。そうなれば、より自分たちの地域に近い生活が始まるわけですから、何とかして「楽しいこと」でつながる仲間を作りたいと考えるようになりました。
子供たちのためだけでなく、自分も含め、親も解放され、楽しむ場がほしいと感じていたのです。楽しいことをやってそこに集まる人たちが、親であれ、子供であれ、個人であれ、ゆるく仲間になれたら素敵だろうな、と妄想をめぐらし始めました。雅子も、映像よりも音を楽しむことが多く、特に生音、実際に歌ってもらうことが大好きでしたし、私自身ももともと、アフリカの音楽には興味があったので、ドラムの先生にきてもらってクラスをつくり、そこに親子で参加できるようにすれば自分がドラムの知識や経験がなくてもいいのでは、、と閃きました。

そこでアフリカのドラムの先生を探すことから始めました。偶然に手にした雑誌にコンゴ出身のドラマーの取材記事がのっていたのに飛びついて、その方のライブにいってみることにしたのです。奥様が日本人で当人も在日期間が長いので、すぐ趣旨を理解してくれ、とんとん拍子で近隣の障害者施設でまずはライブをやる企画が決まりました。聞いている人にも簡単なダンスで参加できるような場面も取り込んだ楽しいライブでした。聞きにきてくれた方たちにアフリカの太鼓を習いませんかという呼びかけのチラシを配ったりして、次はクラスづくり、と考えていました。
ですが、実際は、二人の子供たちの世話と仕事と新たに加わった自分の親の介護とでなかなか次のステップに進めずにいたところ、人から薦められて読んだ本が「ドラムサークルスピリットDrum Circle Spirit :Facilitating Human Potential Through Rhythm」(Arthur Hullアーサー・ハル著 1998)というアメリカ人のドラマーが書いた本でした。それは、楽譜どおり、決められたリズムを叩く太鼓のクラスではなく、輪になって座り、リズムを合わせる以外、規則のない、「今、ここ」の音楽作り、繋がりを楽しむ活動でした。
アフリカのドラマーを師に仰ぎ、実際に現地ツアーにも参加していた著者が、文化の枠にとらわれず、リズムでつながるのをお手伝いするドラムサークルファシリテーターという役割を開発していったのです。非言語でつながるリズム、、、年齢、国籍、障害の有無を問わない音楽活動、でも実際は人との繋がりを紡ぎ出すマジック。
ちょうど日本でこの活動を紹介しようとしていた人がその著書を日本語に訳すのに、翻訳者を探していたこともあり、翻訳作業を手伝う幸せにあずかりました。その後は、来日するごとに仕事としてお手伝いできるようになり、実際自分でも不定期でしたが呼ばれて養護学校、保育園、学童などでドラムサークルをするようにもなりました。
そこで、いよいよ地元でも当初の目的を達成するべく、小規模のドラムサークルとアフリカのドラム(ジェンベ)のレッスンを組み合わせたクラスの開催に至ったのが2013年でした。以後、ほそぼそと月1回のペースで地元に近い音楽室で親子で参加できるクラスを雅子も参加して、開催するようになりました。少人数のクラスでしたが、小さなコミュニティーはできていきました。(コロナがくるまでは…)
私にとってコミュニティーの作り方を最初に学ばせてくれたのは、このドラムサークルの世界でした。そこに雅子も役割をもって参加していたのです。クラスでは自然と雅子も紹介する場面があり、参加者の方と同じように、ヘルパーさんといっしょに楽器をもって、リズムに加わることができました。
地元での重度の障害者のための住まいを求めて
安定した20代前半を過ごしたあと、娘はまた少しずつ衰えをみせるようになりました。
あかちゃんのとき言われた「20歳ごろまでしか生きられない、」のお医者様の予想を悠々と乗り越えたものの、重度の障害者は健常な方よりも早く老化が始まると言われています。健康上の課題が毎年ひとつひとつ増えていくようでした。それまで長く入院せずに済んでいたものの肺炎で再びよく入院するようにもなってきました。
障害者に関する法律も、「措置」から「契約」へと大きく舵をきった2003年支援費制度、2005年のより受益者負担の色が濃くなった障害者自立支援法、「自立」より「人権」に重きをおいた2012障害者総合支援法とめまぐるしく変わっていきました。この流れの中で、障害者の住まいもいわゆる都心から遠く離れた大規模な施設での生活から、地域での家庭に代わる少人数を単位としたグループホームへの流れができていきました。
しかし、重度の障害者、特に明快な意思疎通が難しい、重症心身障害者、医療的ケアも日常的に必要とする障害者については、国の制度のひろう基準以上のケアが必要なため、人員配置基準が十分とはいえず、単体での経営が難しいことから、全国的にもなかなか実現が難しく実現にこぎ着けたケースは非常に限られていました。特に地代の高い大都市部での運営は資金的にリスクとなるため、なかなか実現ができないまま現在にいたっています。
娘のいく末の不安が募り始めた頃、通所しているデイケアで紹介された映画のチラシが「普通に生きる」( http://www.motherbird.net/~ikiru/ )という富士市で重症心身障害者のための通所施設、グループホームを開所させた親のグループの数年間にわたるドキュメンタリー映画の案内でした。これは見に行くしかないと時間をつくり見にいきました。
衝撃を受けました。すでに自分たちの力でここまでやった人たちがいるのか…。そのころ勉強会をいっしょにしていた親御さんを誘って、早速現地を訪問させてもらうことにしました。当時のセンター長さんが丁寧に、各施設を案内し、説明してくれました。この映画は身近にいる重度障害者の親御さんにも見てもらいたいと、通所施設先で交渉して、映画の上映会を行いました。この映画との出会いが以後2016年に特定非営利活動法人ソラマを立ち上げる原動力になりました。 (つづく…)