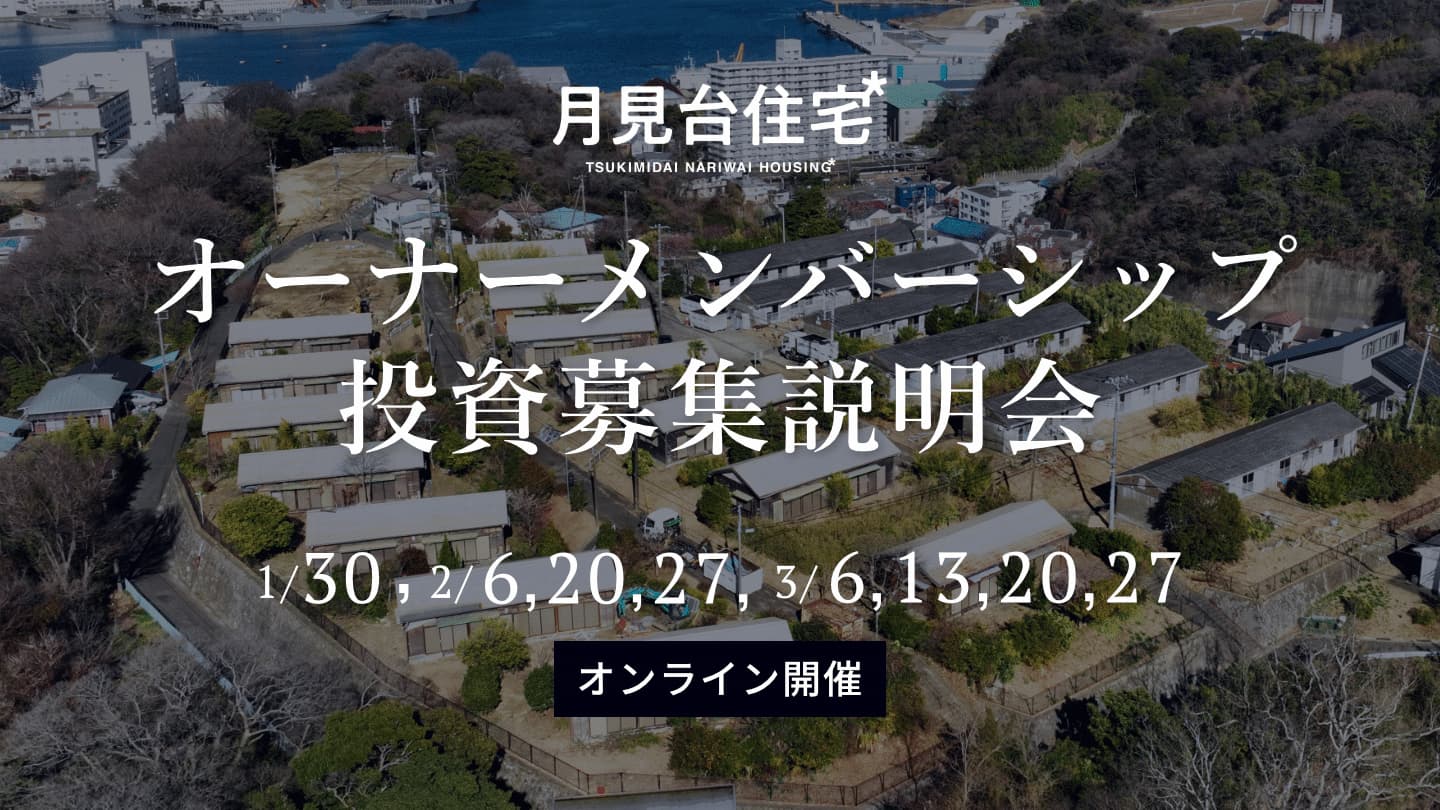「地域の未来に、本気で向き合う投資」投資家インタビューvol.19 西日本旅客鉄道株式会社 地域共生部

「地域の未来に、本気で向き合う投資」——JR西日本が三豊に込めた想い
ローカルIPOサミット 投資家インタビュー/西日本旅客鉄道株式会社 地域共生部
「地域と鉄道は、不可分一体なんです」
そう語るのは、西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)地域共生部の担当者。香川県三豊市でエンジョイワークスと瀬戸内ビレッジが展開するソーシャルファンドプロジェクトに、JR西日本が出資という形で参画しています。企業として投資する意味や意義は? その背景とローカルIPOへの期待について聞きました。
(写真左:株式会社JR西日本イノベーションズ 代表取締役社長 川本亮さん、同右:西日本旅客鉄道株式会社 地域まちづくり本部 地域共生部 次長 南條兼人さん)
「地域にお金が巡る」ことへの共感
――企業が地域のプロジェクトに投資する。規模が大きな企業にとっては、その選択に至るまでのハードルは高いような気がします
投資を検討する上で、最も共感したのは“地域にお金を循環させていく”という視点でした。三豊での取り組みは、まさにその課題に向き合っていて、外部プレイヤーと地元の人々が丁寧に対話しながら積み上げてきたプロセス、そして自走可能な事業モデルとしての成長性がありました。そして、プロジェクトリーダーの秘馬さん(古田秘馬さん:瀬戸内ビレッジ代表)の思いや行動力に引き込まれたことも、大きかったかもしれません。
「ハコモノ投資ではなく、“地域の土壌を豊かにする”」。地域に人材を根づかせ、資金の循環をつくり、そこで暮らす人たちが当事者として関わっていける構造を支援したいと考えました。これは私たちが目指す“地域共生”の実践でもあります。
そしてもうひとつ、このプロジェクトに大きく共鳴したのが「投資家とプレイヤーが対等な関係で関われる仕組み」でした。ファンドという仕組みを通じて、大企業も個人も“同じ船”に乗れる。出資者として、リアルな現場にアクセスし、共に未来を描く立場になれる。それはこれまでの大手主導の構造とは違う、新しいパートナーシップの形であると感じました。これは、地域にとっても企業にとっても大きな意味を持つと思います。
――プロジェクトに関連して、三豊にも実際に足を伸ばしたようですね
私たちは鉄道会社なので、本業の鉄道運行に加えて、駅前や商業施設などの開発を多く手掛けています。その反面、地域活性の文脈で「プレイヤーになることの難しさ」も感じていました。三豊のプロジェクトを知り、「現地で動いているプレイヤーと“共働”することで、新しい形の“共創”ができる」と考えました。不動産開発やハコモノ、目先の収益や表面的な賑わいではなく、「地域の土壌を耕す」ような、地元に根差した人材や仕組みを育てていくアプローチ。地域の方々が主体となって動き、そこに外から投資家が関わる「ローカルIPO」という構想は、まさに私たちが目指していた方向性と重なっていました。
ローカルIPOと「地域共生」
──企業も個人も同じ“株主”になれる。なかなかイメージしづらいと思いますが、今回はJR西日本が先鞭をつけてくれました
ローカルIPOの役割の一つは、地域の「稼ぐ力」を育てることだと思っています。いま、地方では人材の流出や空き家の増加、観光の偏在など多くの課題がありますが、それらを“地域発”で解決しようとしているところに未来を感じます。もう一つ、「投資のあり方」そのものを再定義するきっかけになる動きだと思います。私たちは今回、出資という形を取りましたが、これは単なる資金提供ではありません。企業も個人も同じ目線で、地域の未来にコミットできる時代に入ったと感じています。
そうした出資の先には「地域とともに歩む企業」としての新しい姿があると信じています。地域のレガシー企業とつながるツールとしても、ローカルIPOのような仕組みは有効だと思っています。ファンドによる投資(資金)が地域に根づき、次の事業、次の担い手を育てる循環を目指す。それがJR西日本の“地域共生”というビジョンと合致していました。
──鉄道事業者が「地域共生」に重点を置く理由を教えてください
本質的な話ですが、鉄道インフラは、その地域に人が動いてこそ価値があるのです。都市だけでなく、中核都市やローカルエリアの元気がないと、鉄道そのものが停滞してしまうという危機感がありました。私たち、地域共生部が掲げているのは「企業も個人も同じ目線で地域に関わる」というビジョン。単なる開発ではなく、地域に「生き生きとした人」がいる状態をつくる。そんな“共生”のあり方を模索している中で、三豊のプロジェクトに出会ったのです。
「地域共生とは何か?」を考え続ける中で、このプロジェクトは私たちにとってひとつの“気づきの場”になりました。それは、「目に見える収支」では測れない、地域と向き合うことを再確認する場でした。単なる収益性ではなく、社会的意義のある取り組みにどう投資していくのか。「ファンドの仕組みを使えば、個人も企業も同じ土俵で、地域と本気で関われる」。その言葉のとおり、ローカルIPOという考え方は、単なる資金調達の枠を超え、新しい“関わり方”の可能性を切り拓いています。そんな「地域共生の“教科書”」を三豊から発信している実感があります。

地域共生のダイヤグラム(同社ウェブサイトより)
西日本旅客鉄道株式会社ウェブサイト(地域共生の取り組みページ)
https://www.westjr.co.jp/company/action/region/
地域共生という言葉には、私たちが「地域と対等な立場で共に生きていく」という想いが込められています。鉄道会社としては、これまで「地域のために何かする」と、上からの姿勢になりがちだったんですが、これからはむしろ、地域と一緒に“同じ船に乗る”ような関係性が求められていると思っています。例えば、私たちの部署では岡山県で行われている「森の芸術祭」の企画協力も行っていますが、地元産業の活性化、地元資源の磨き上げなど、「地域の稼ぐ力」を育てたり、ブランディングしたり。数字だけでなく、社会的なインパクトをどう生み出すか──それも含めた地域共生なのです。
私たちは常に、「地域と共に生きる企業でありたい」と考えています。鉄道だけに頼るのではなく、地域の力を信じ、共に育てていく。それは決して派手なことではないかもしれませんが、未来社会に向けた私たちの存在意義を発揮できる領域だと思っています。「いつか戻ってきたいまち」「ただいまと言えるまち」──そんなふうに思ってもらえる場所を、地域の方々と一緒に育てていきたいと思っています。

エンジョイワークスの事業の現場へも視察に。「ただいまと言えるまち」のヒントを学び取っていったようです
せとうちパレットプロジェクトウェブサイト
https://www.jr-odekake.net/setouchi-palette/