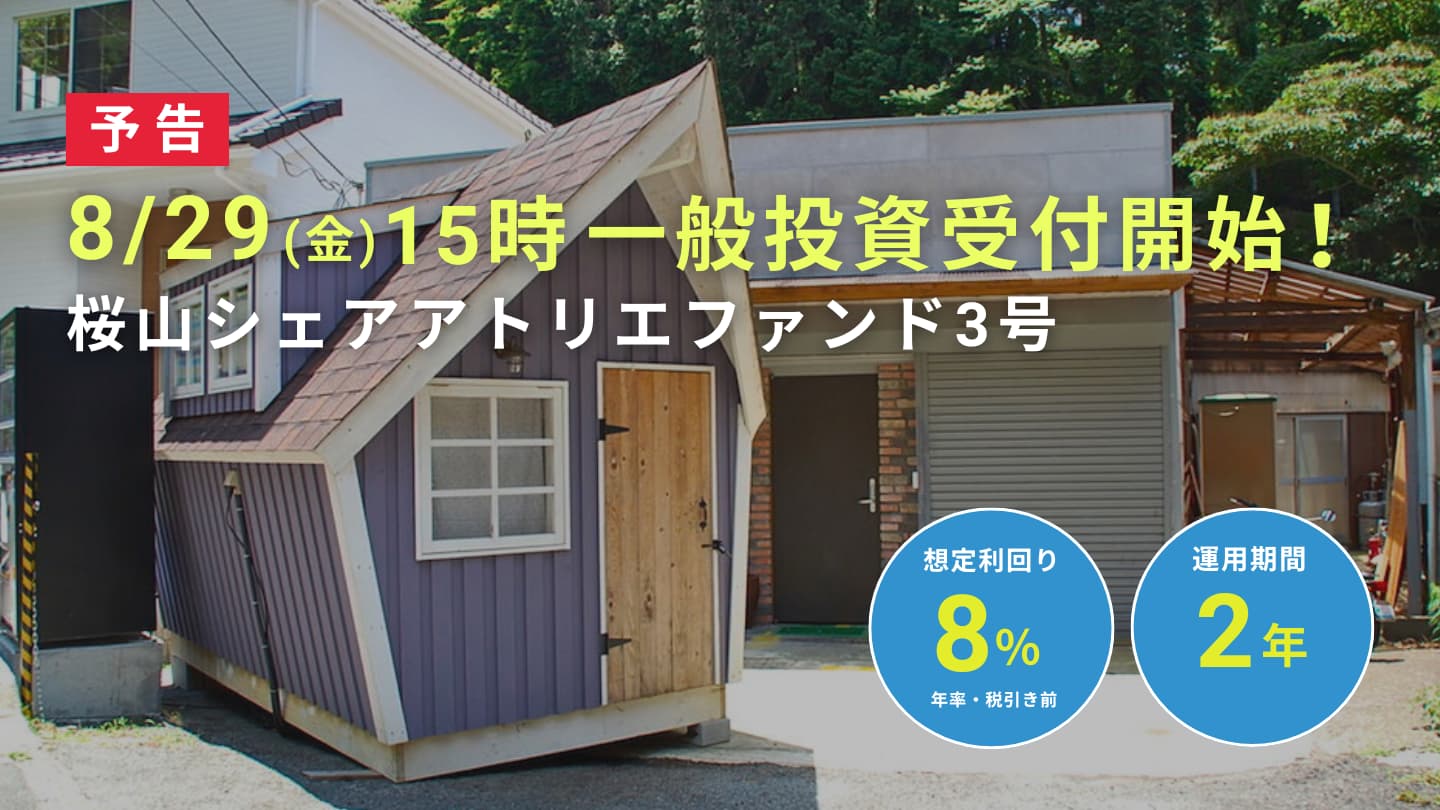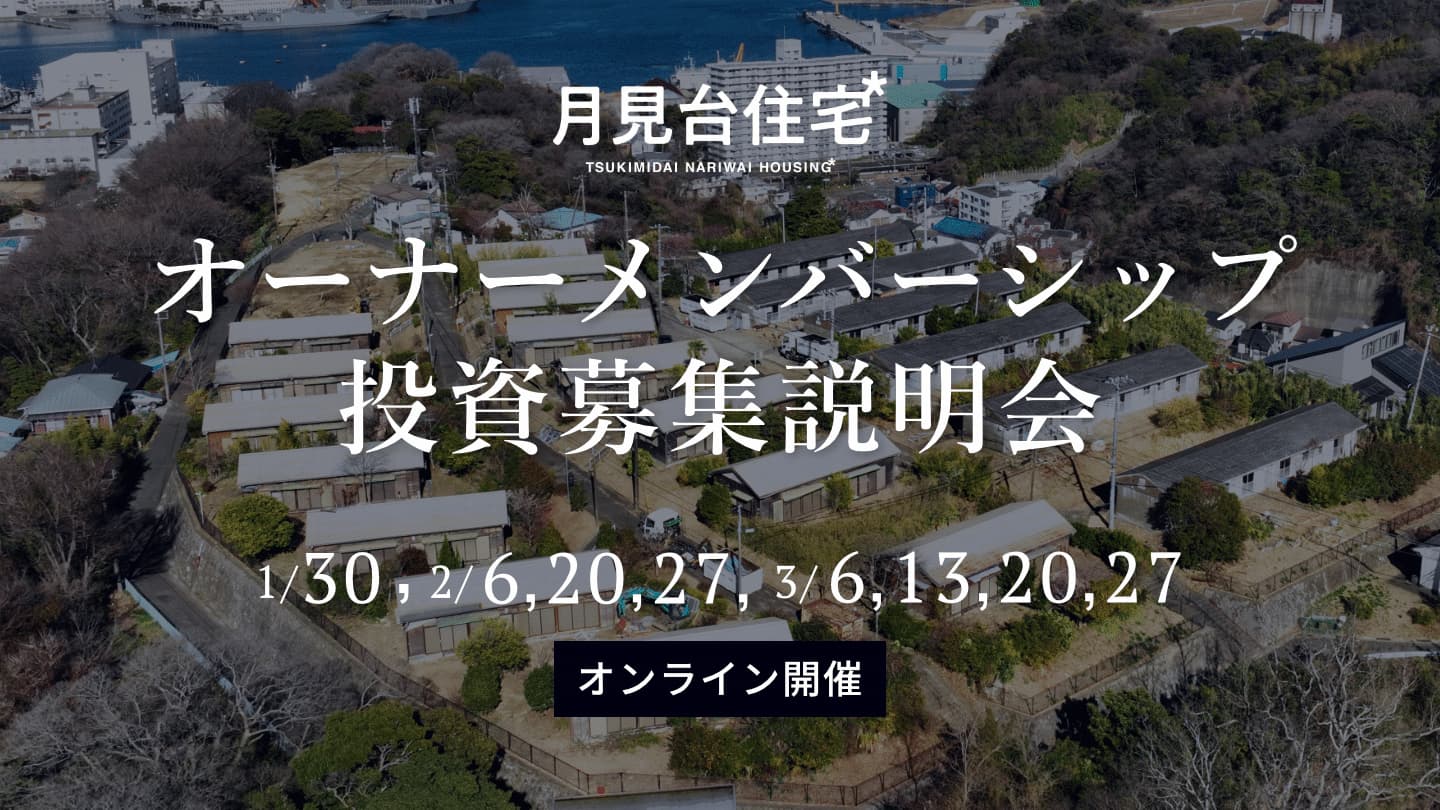地域で事業を磨き上げている人たちを「応援する」投資家インタビューvol.20 日本航空株式会社 関係・つながり創造部

地域で事業を磨き上げている人たちを「応援する」。関係人口・株主人口という新しい概念への共感
ローカルIPOサミット 投資家インタビュー/日本航空株式会社 関係・つながり創造部
国内外の企業にとって、事業の足元を見つめ直すきっかけになったのがコロナ禍かもしれません。これまで当然だった「旅客を輸送する」という前提が失われた公共交通事業者も、大きな変革を求められました。「地域を支える存在」「コミュニティづくりの一員」へと役割を広げる動きが加速。つまり移動そのものよりも「移動が生む関係性や価値」へのシフトが始まったと言えます。そうした動きの中で、地域と共創し「創造」をしていく手段として、香川県の三豊にあるソーシャルファンドプロジェクトの投資に参画した日本航空(以下、JAL)。2024年に設立された、「関係・つながり創造部」部長の関谷岳久さんに、投資に至った経緯と想いを聞きました
地域活性化 の主人公は「地域」
――企業が地域の事業に投資する。本来であれば、地域のプロジェクトにそのように関わるのは難しいことだと思います
今回、この取り組みへの投資を決めた背景には、「地域との本当のつながりを築きたい」という想いがありました。コロナ禍で移動が止まり、あらためて自社の社会的意義を解き直した際、人と人、地域と都市部・世界の「関係とつながり」を創出する会社なのだと行きつきました。私たちの部署は、日本各地そして世界でどのように「関係・つながり」を創っていくのか?というミッションがあります。
実際に三豊を訪れて、古田秘馬さん(株式会社瀬戸内ビレッジ代表)の話を聞き、地域の人々が自らビジネスを創り、自立的に経済圏を回している姿に強い衝撃を受けました。誇りを持って地域を育てている。「地域との継続的なつながりを持って成長させている三豊なら…単なる出資者ではなく、仲間として関われる」と確信しました。一般的には、企業の投資判断は厳しくリターンの計算が必要になります。ただ今回は、そういったスケール重視の文脈だけではなく、「株主人口を増やす」というメッセージ、つまり「関係・つながり」を生むための新しい形の投資と捉えました。だからこそ、ハードルは高かったものの、共感を軸に判断できたと考えています。
――ローカルIPOの考え方について、企業としてどのように解釈されていますか? 地域と企業、投資の新しい関係性という視点で見るといかがでしょうか?
投資で共創する仕組みであるローカルIPOを知ったのは、ちょうど「地域に根差した事業とは?」と考えていた時期でした。一過性の観光には限界があり、地域との継続的なつながりがあるところからはじめていきたい、と思っていたタイミングでもありました。
この「仕組み」は、地域の自立性を重視した新しい投資活動の形態として、今後さらに広がりを見せる可能性があると感じました。投資した「株主」が地域の「仲間」として関与して、つながりを深めながら共に成長していく。投資による継続的な関係構築を通じて地域と企業が相互に支え合いながら発展する。株主は、地元のことを知り尽くしている地域住民だけでなく、事業者の「仲間」、そしてそれを応援する立場の人たち。成長を支援する新しい「株主人口」の概念は、地域の発展における重要な要素となるのではないでしょうか。
地域活性化の主役は、やはり「地域」そのものであり、私たちのような企業はその活動を支える立場。株主が地域の「仲間」として共に成長する、という新しい投資モデルは、地域経済の持続可能な発展に貢献するものとして、今後広がりを見せると思います。これまでは地域に関わる手段がなかったと思うのですが、ローカルIPOの仕組みを使って、個人から企業まで、共創しながら成長の段階に携わることができる。いわゆる「株主」というと、権利を有する無味乾燥な立場をイメージするかと思いますが、私は、ここでの「株主」とは「応援する人たち」だと思っています。地域の事業者(人たち)を主役にしながら仲間がつくれる。例えば、個人から企業までさまざまな“株主”たちと「株主ミーティング」といった交流ができたら。株主になった人同士で化学反応が起きるかもしれませんね。
公共交通事業者が「関係・つながり」を重要視する理由
――まさに部署の名称が「関係・つながり創造部」ですが、公共交通事業者でもあるJALがここに力を入れる理由を教えてください
昨年夏に、「移動を通じた関係・つながり」を創造する未来を描いた JAL FUTURE MAPを公開しました。そのなかで私たちの部署は「関係・つながり創造部」という名称の通り、関係人口の拡大に加え、地域社会やコミュニティとの関わり度合いを高め、何度も訪れたくなるような仕組みを作っていく役割があります。日本国内はインフラが整っていると言われますが、それは都市部とか首都圏の話で、地域の過疎化は進んでいます。こうした状況の中で、私たちは「地域」でなにができるのか。地域が元気になることが、私たちの国内航空ネットワークにも良い影響を与え、活性化を通じて私たちの事業の成長にも循環していく。つまり、単に飛行機を運航するのではなく、地域が元気になること(していくこと)が重要です。
JAL FUTURE MAPウェブサイト
https://www.jal.com/ja/futuremap/
私たちの会社では、地域に対する理解を深めるために、スタディツアーや「旅アカデミー」などの商品を扱っていますが、三豊もその「旅と学びの体験型プログラム」の現場のひとつ。地域で実際に「関係・つながり」を生み出している人たちに学びに行く旅です。いわば地域のファンを増やすお手伝い。国内外の姉妹都市交流にも「関係・つながり」のチャンスがあると思いますが、最初はトップ同士が握手を交わすだけの形式的なものが多く、時間が経つと交流が途切れてしまうことがあります。そこで、私たちが「縁を積極的につなぎ直す」―そんなこともできればと思っています。

三豊での「旅アカデミー」の様子。講師は地元事業者の今川宗一郎さん
――移動する目的やその先のストーリー、街で頑張っている人たちに伴走するということですね
最近では「二地域居住」などが注目されていて国も力を入れています。単に需要のある場所に飛行機を飛ばすのではなく、移動そのもの、移動した先に価値があるという考え方が重要です。そのモデルケースとなり得るのが三豊。この地域を知れば知るほど、事業に関わるみなさん、二拠点などで活動している方々ともに幸せそうで、自分の居場所を持っていて、自分の言葉で話せる人が多い。「街全体を盛り上げるのは自分たちなんだ」と自信と自覚がある。そんな地に足が着いている人たちとの継続的なつながりとして関わる手法が、投資や(旅アカデミーなどの)事業であるということでしょうか。
また、国内ではインバウンド需要の高まりが注目されていますが、各地域までインフラが整っていないという現状もあります。オーバーツーリズムやインフラの偏在など、いわゆるインバウンドの不均衡が国内で起こっています。そんな現場を目にするなかで、公共交通事業者という目線と「関係・つながり」という視点で、地域のインフラづくりの「ファン」になるとか、その地域ならではの二次交通にも参画できるかなと思っています。
今回の投資は、(ローカルIPOという)新しい取り組みの中で、改めて地域という「舞台」での関係・つながり、創造が大事なのだなと考えるきっかけになりました。成長軌道に乗せるための伴走の仕組みに参加できる。そんな関わり方を考えながら、私たちは三豊で始まった「ローカルIPO」の仕組みをしっかり横展開していきたいと思っています。
日本航空株式会社ウェブサイト
https://www.jal.com/ja/